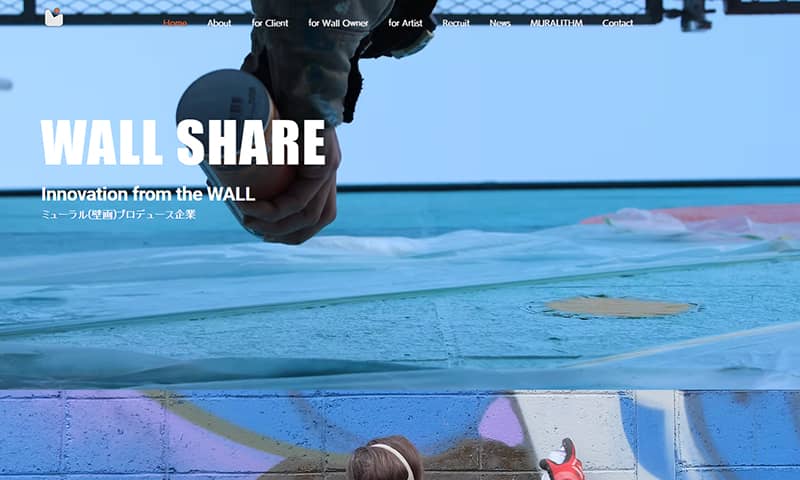大阪のミューラルアート事例
近年は町おこしのきっかけや、製品の広告にも使われるミューラルアート。こちらのページでは、大阪府でのミューラルアートの事例を紹介します。「壁を有効活用したい!」と考えている自治体・企業は、ぜひ参考にしてみてください。
富田林市市民会館
| CLIENT | 富田林市 |
|---|---|
| PROJECT | 富田林市ミューラルプロジェクト |
| VENUE | 富田林市市民会館 |
| ARTIST | TWO-ONE |
地元・喜志小学校の5年生とのワークショップから着想を得ており、粟ヶ池にまつわる伝説がテーマとなっているミューラルアート。大胆に描かれた竜が迫力満点で、今にも動き出しそうな躍動感を持っています。
長居公園
| CLIENT | わくわくパーククリエイト株式会社 |
|---|---|
| PROJECT | わくわくMURAL |
| VENUE | 長居公園 |
| ARTIST | Gravityfree |
2024年8月から、ヤンマーフィールド長居近くの壁に展示されているミューラルアートは、djow(Toshio ono)と8g(Eiji miyata)の二人組アーティスト「Gravityfree(グラビティーフリー)」による作品です。
動き出しそうなエネルギーを感じさせるこのミューラルアートは、スポーツ、自然、アート、学びといった多様なアクティビティを楽しむことができる長居公園にぴったり。訪れた人々に、ワクワクするような感動を届けてくれます。
大阪でミューラルアートを依頼するメリット
地域活性化が狙える
大阪市では住民主体のアートプロジェクトがここ数年で加速し、壁面を活用したミューラルが周辺経済に波及効果を生んでいます。代表例が淀川区で進む「淀壁」プロジェクトで、2024年度だけでも5ヵ所に新作が追加され、周遊型まち歩きイベントによる来街者の飲食・物販消費が顕著に伸びました。アーティストと地域企業が協働し、自主財源やクラウドファンディングで運営する仕組みは、行政補助に依存しない持続可能なモデルとして注目されています。
さらに 2025年大阪・関西万博を控えるなか、行政サイドもストリートアートを観光資源と位置づけています。此花区の「MURAL TOWN KONOHANA」は 16ヵ国 3作品が点在し、ミニツアーやフォトウォークが連日開催されるまでに育ちました。これらの成功事例は、店舗オーナーや自治体が自施設壁面にミューラルを導入することで、単なる装飾を超えた「動く広告塔」「街の目印」という機能を獲得できることを示しています。
SNS映えする
インバウンド客を含める観光客は、大阪城や道頓堀など定番観光地に加え、ローカルアートスポットを「自分だけの発見」として共有する傾向があります。ミューラルは言語を介さずにブランドストーリーを伝えられるため、観光客向けの屋外広告としても優れたコストパフォーマンスを発揮します。
ミューラルアート依頼の流れ
【事前準備】目的・コンセプト・予算の明確化
依頼の第一歩は「なぜ描くのか」を言語化することです。店舗なら集客導線強化、企業なら理念浸透やES、自治体なら地域ブランディングなど、目的によってデザインも施工規模も大きく変わります。加えて壁面サイズ・素材・周辺導線・照明条件など物理的制約を整理し、想定効果をKPIで可視化すると見積もり比較や効果測定がスムーズです。
同時に概算予算帯を決めておきましょう。先に上限額を共有すれば、アーティスト側が制作技法や色数を調整して提案できるため、後のリテイクを減らせます。
➀:【アーティスト選定】直接依頼vsエージェント利用
ミューラルアートや壁画、ウォールアートの制作を直接契約する利点は制作費を抑えやすく、双方の意思決定が速い点にあります。一方でスケジュール管理、許可取得、安全管理を依頼者側が主導する必要があり、社内リソースが限られる企業や自治体には負担になりがちです。
エージェントを介する場合、コンセプト設計から施工管理、PR施策まで一気通貫で対応できる体制が整っています。手数料は乗りますが、複数アーティストのポートフォリオ提案や契約書類のリーガルチェックを任せられるため、ブランド規模が大きい案件や屋外の大壁面ではリスクヘッジとして有効です。
②:デザイン決定とラフ提案
ヒアリングを経て、アーティストはラフスケッチや 3D モックアップでイメージを可視化します。色彩計画は周辺景観条例や企業 CI に合致するかを確認し、夜間ライトアップの有無や視認距離による見え方も検証します。大阪市中心部では高さ制限や眺望規制があるため、遠景での可読性を意識した大胆な構図が選ばれる傾向があります。
ラフ確定後、着彩カラーパレットや素材サンプルを提出し、依頼者が最終承認を行います。ここで修正回数や追加料金の扱いを契約書に盛り込み、将来的な二次使用(販促物やSNS広告)に関する権利範囲も明文化しておくとトラブルを防げます。
③:【制作準備】材料手配・許可申請・スケジュール調整
屋外施工では耐候性塗料や防カビコーティング材、足場や高所作業車の手配が必要です。大阪市内で道路占用を伴う場合、屋外広告物許可と占用許可を同時に取得しなければなりません。行政オンラインシステムから電子申請できるようになったため、着工3週間前までに書類を提出し、審査期間を見越して工程を組むのが一般的です。
また梅雨時期や台風シーズンは雨天順延が発生しやすく、屋外案件は 1~2 週間のバッファを取るのが安全です。屋内の場合でも養生範囲 1.5~2 mを確保し、営業中店舗なら低臭塗料や営業時間外の夜間作業を検討するといった配慮が求められます。
④:実制作から納品・確認まで
着工後は下塗り、下描き、着彩、本塗装、トップコートの順に進行します。10 ㎡クラスなら 3~5 日、30 ㎡超の大型壁面では 1~2 週間が目安です。途中段階で依頼者が現地確認し、色味やモチーフの微調整を行うケースもありますが、ラフ承認後の大幅変更は追加費用が発生するため注意が必要です。
完成後は依頼者・アーティスト・施工管理者が三者立会いで検査し、色むらや剥離がないかをチェックします。問題がなければ引き渡し書を交わし、保証期間(屋外で 1~2 年が一般的)とメンテナンス方法を文書化して納品完了となります。
費用相場と予算相談のポイント
費用の構成要素
ミューラルの見積もりは大きく「アーティストギャランティ」「材料費」「足場・養生費」「交通・宿泊費」「許可申請・警備費」「ディレクション費」の6項目です。屋内限定や低所作業なら足場費が不要になる一方、高所や複雑形状の壁面では足場だけで総額の 15~20%を占めることも珍しくありません。検査費・保険料・撮影費などのオプションもあるため、必要項目を洗い出してから比較することが肝心です。
予算交渉・コスト削減のコツ
費用圧縮を図るなら、下記の3つが有効です。
- 壁面サイズではなく「描画範囲」を限定する
- デザインをモノクロや限定色に絞る
- 屋内の場合は営業外の深夜・早朝帯を避けて平日日中に作業日程を組む
また素材支給や足場共同手配など発注者が一部リスクを負担する提案をすると、ギャランティが下がるケースもあります。複数社相見積もりを取る際は、必ず費用項目を合わせて比較しましょう。「デザイン費込み」「トップコート別途」など表記がまちまちだと安い見積もりに飛びついても追加費が膨らむ恐れがあります。
依頼時の注意点とチェックリスト
屋内・屋外施工の違いと養生・足場の留意点
屋内は塗料飛散と臭気対策が最優先です。低VOC塗料や水性アクリルを使い、空調を止めるタイミングを事前調整します。屋外は紫外線・雨風への耐候性を確保するため、フッ素樹脂系クリアでトップコートを二重施工するのが標準仕様になりつつあります。足場は安全帯・ヘルメット着用の義務だけでなく、歩行者導線のカラーコーンや警備員配置も見積もりに組み込まれているか確認しましょう。
許可・条例・安全対策
大阪市では屋外広告物条例に基づき、色彩制限区域や眺望保全区域での大型壁面は事前協議が必須です。占用許可を伴う場合、図面・意匠図・構造図を添付して電子申請し、審査料を納付する流れになります。高所作業を伴う現場では労働安全衛生法の特別教育を受けた作業員を配置し、工期が 7 日を超える場合は現場代理人の常駐が求められる点も見逃せません。
維持管理・メンテナンス計画
トップコートの再塗布目安は屋外で3~5年、屋内で5~7年です。施工時に余剰塗料の色番号を記録し、補修用として密閉保存しておくと後年のタッチアップが容易になります。SNS 上の写真で色褪せが目立つとブランドイメージに直結するため、定期点検とクリーニングを年間保守契約に含めておくと安心です。
Sponsored by
WALL SHARE株式会社
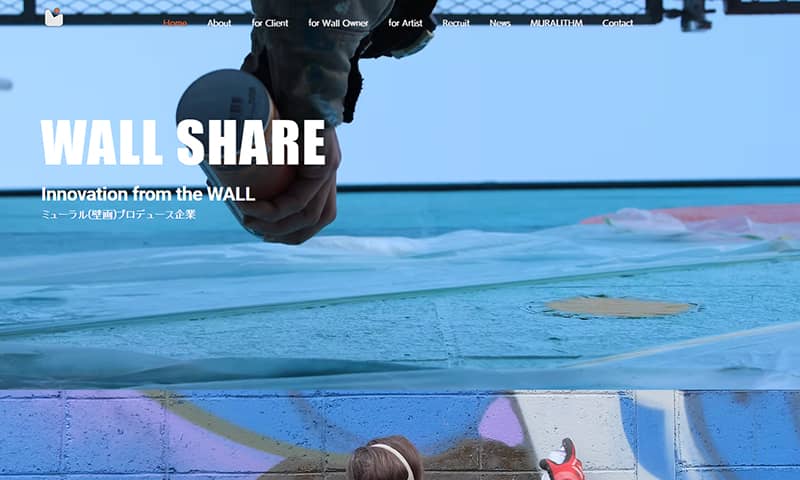
プロデュースし続ける
壁の確保から、その場所・コンセプトに相応しいアーティスト選定、そしてアーティストが最大限クリエイティブを発揮できる環境作りを行うミューラルプロデュース会社。
アディダス、AVIOT✕アイナ・ジ・エンドなど、「ミューラル広告と言えば」で思い当たる多くのアートを手掛け、その数は2025年1月現在で170にものぼる。